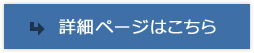ランドセルにタブレット収納は必要?タブレット端末収納タイプのランドセルとは?

政府は完全デジタル教科書化に2025年までに本格導入開始することを目標としており、2024年度までに全国の小中学校の生徒に対し、1人1台のパソコンやタブレット端末が使える環境を整えて、タブレットで授業を受けることを推奨しています。
すでに、小学校の授業では英語やプログラミングなどといった教育改革が始まっていることもあり、タブレット学習が取り入れられて、毎日持ち帰っているお子さんも多いのではないでしょうか。
今後は、全国の学校でタブレット端末の配布や購入をすることになるので、毎日の登下校でタブレットをランドセルに入れて持ち運ぶということになってきます。
年々、各メーカーや工房でタブレット端末収納に対応したモデルや、タブレットケースをセットにしているモデルなどが増えてきています。

『周りのお友達とはちょっと違ったおしゃれなランドセル』
「ARTIFACT(アーティファクト)」
ARTIFACT(アーティファクト)は「芸術品」という意味を持っており、株式会社ラ・ポンテが展開する2021年度に新登場したブランドです。2024年度も個性的でスタイリッシュなデザインの新モデルランドセルがラインナップされています。
>タブレット端末収納にも対応しており、シンプルなのに周りのお友達のランドセルとはちょっと違った個性的でおしゃれなランドセルです!ぜひチェックしてみてください!
ランドセル選び大容量+タブレット収納は必要?
新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、自宅でのリモート授業などが行われることもあり、端末導入のスケジュールが大幅に前倒しされました。2021年4月から文部科学省が進めている「GIGAスクール構想」がスタートしていることもあり、多くの小中学校で、1人1台タブレット端末が導入されて授業で活用されるようになっています。
「GIGAスクール構想」
「GIGAスクール構想」とは、文部科学省が進めている、小中高等学校などの教育現場で、1人1台のパソコンやタブレットなどのICT端末を活用して、子ども1人ひとりに適したより深い学びが実現できるようにする取り組みです。

デジタル教科書が本格的に導入される予定の2024年度までは、タブレット端末を導入している学校としていない学校があり、現在、タブレット端末を使用した授業をして持ち帰っている小学校では、教科書などの荷物+タブレット端末と、毎日重いランドセルで登下校することになります。
タブレット端末収納タイプのランドセルには、タブレット端末をきちんと固定して収納できたり、タブレットに付属するコードを収納したり、ランドセルにタブレットを入れているときにモバイルバッテリーで充電できる機能があったりなど、さまざまな工夫がされているので、ランドセルを選ぶときの候補に入れておいてもいいでしょう。
大容量タブレット収納に対応しているランドセルの特徴とは?

タブレット端末を使用した授業が始まると、タブレットを学校に置いていく場合は別ですが、持ち帰る場合にはランドセルに収納して登下校することになります。
小学校で使用するタブレット端末の多くは、基本的にA4フラットファイルサイズ対応の大容量ランドセルであれば、タブレットを収納することができます。
タブレット端末収納に対応したランドセルであれば、よりデジタル端末への衝撃を和らげることができるので、タブレットを安全に持ち歩くことができるので安心して収納することができます。
タブレット収納に対応しているランドセルの特徴
・専用の収納スペースがある
・タブレットケースを固定できる
・ランドセルの底板に衝撃緩和材が入っている など
タブレット収納に対応していないランドセルでも、大容量ランドセルであればクッション素材のタブレットケースに入れて、小マチなどに収納することができます。
しかし、ランドセルが頑丈に作られているとはいえ、タブレット端末は精密機器なので、ランドセルのロックをし忘れていた場合、中の荷物と一緒に飛び出してしまって破損や故障してしまうことがあるかもしれないので、収納したタブレットが落ちないような工夫がされているランドセルがの方が安心です。
入学する小学校によって、タブレットは学校保管が原則で持ち帰りをしなかったり、学校から貸与されるタブレットのサイズが収納ケースやポケットと合わず、ランドセルに収納できないということもあるかもしれないので、購入前に学校へ確認したうえで準備をしましょう。
2024年度 PC・タブレット収納対応のおすすめランドセルを紹介!
 フィットちゃん
フィットちゃん

フィットちゃんの大容量ランドセル「楽スキッ」は、メインポケットが12cm、サブポケットは最大5㎝に伸びるタイプです。
メインポケットとサブポケットで荷物を分けて入れられるので整理整頓して入れられます。
「大容量ワイド」は、メインポケットが13.5cmと楽ッションタイプに比べ1.5cm広くなっており、ノートが4冊分程度多くメインポケットに入ります。
どちらも、底板に入っている衝撃緩和材が、タブレットやノートパソコンなどデジタル端末の衝撃を和らげてくれるので安心です。
シュシュ・フローラワイド 安ピカッ+楽ッション タイプ
★大容量ワイド タイプ
◆期間限定価格:68,000円(税込)
◆カラー:全4色
◆サイズ:A4フラットファイル収納サイズ
横幅 23.3cm×高さ 31cm×マチ幅 13.5cm
◆主素材:クラリーノ エフ
◆重量:約1,200g

本体カラーに合わせて施されたサイドのボタニカルフラワーの刺繍と、優しい色使いでシンプルな高学年になっても甘すぎない、かわいらしいデザインのランドセルです。
メインポケットの奥行が1.5cm大きい大容量タイプで、肩への負担が軽減できる楽ッション、雨の日や暗い夜道で車のライトに反射してピカッと光る安ピカッなどの機能が搭載されています。
![]() 「シュシュ・フローラワイド 安ピカッ+楽ッション タイプ」の詳細はこちら
「シュシュ・フローラワイド 安ピカッ+楽ッション タイプ」の詳細はこちら
グッドボーイDX 安ピカッ+楽ッションタイプ
★楽スキッ タイプ
◆期間限定価格:62,800円(税込)
◆カラー:全4色
◆サイズ:A4フラットファイル収納サイズ
横幅 23.3cm×高さ 31cm×マチ幅 12cm
◆主素材:クラリーノ タフロック NEO
◆重量:約1,210g

本体にはクラリーノの中で最も傷に強い素材「クラリーノ タフロック NEO」が使用されており、スポーティでカッコいい大マチステッチが特徴の元気な男の子にぴったりなランドセルです。
肩ベルトの分厚いクッション「楽ッション」がしっかりと肩に固定されて体にフィットし、雨の日や暗い日はピカッと光る安ピカッ機能がついており、高機能+軽い背負心地で安心安全に使用することができます。
![]() 「グッドボーイDX 安ピカッ+楽ッションタイプ」の詳細はこちらから
「グッドボーイDX 安ピカッ+楽ッションタイプ」の詳細はこちらから
 キッズアミ(KIDS AMI)
キッズアミ(KIDS AMI)
キッズアミのランドセルは、大マチ幅12cm+小マチ幅が最大約8cm拡がる大人気モデルのペリカンぽっけに、大マチ内部に新機能であるタブレットポケットがついたモデルや、大マチ幅が13.5cmのモデルなどがあり、全てのモデルが大容量で大マチに11インチのタブレットがスッポリ収納することができます。
ペリカンポッケプラス

◆販売価格:72,600円(税込)
◆カラー:男の子・女の子 各全4色
◆サイズ:A4フラットファイル収納サイズ
横幅 23.5cm×高さ 31.5cm×マチ幅 12cm+8cm
(小マチのファスナー開閉で奥行 12cm+8cm)
◆主素材:クラリーノ タフロック NEO
◆重量:約1,260g

タブレット端末収納タイプのランドセルなので、タブレット端末を持ち帰る場合、タブレット端末をきちんと固定して収納できたり、タブレットに付属するコードを収納したり、ランドセルにタブレットを入れているときにモバイルバッテリーで充電できる機能があったりなど、さまざまな工夫がされているので安心です。
![]() キッズアミ ペリカンポッケプラス【女の子】の詳細はこちら
キッズアミ ペリカンポッケプラス【女の子】の詳細はこちら![]() キッズアミ ペリカンポッケプラス【男の子】の詳細はこちら
キッズアミ ペリカンポッケプラス【男の子】の詳細はこちら
ワンダフルポッケ

◆販売価格:68,200円(税込)
◆カラー:男の子・女の子 各全5色
◆サイズ:A4フラットファイル収納サイズ
横幅 23.5cm×高さ 31cm×マチ幅 13.5cm
◆主素材:クラリーノ エフ
◆重量:約1,190g

「大容量13.5cmマチ」にノートPC・タブレット収納ポッケが追加されたランドセルです。
高品質にこだわった国内生産で、革や金具の素材と加工法、ひとつひとつを丁寧に企画開発された軽量ランドセルです。
![]() キッズアミ ワンダフルポッケ【女の子】の詳細はこちら
キッズアミ ワンダフルポッケ【女の子】の詳細はこちら![]() キッズアミ ワンダフルポッケ【男の子】の詳細はこちら
キッズアミ ワンダフルポッケ【男の子】の詳細はこちら
 池田屋
池田屋
池田屋のランドセルは、小マチが最大4.5cmまで広がるので、十分な容量の大マチと合わせると総マチ幅は最大で16.7cmになり、サブバックで持っていくはずの体操服や水筒まですっぽりと収納することができ、荷物が少ない日は小マチを畳んですっきりコンパクトに調節することができます。
全モデル「パソコン・タブレット対応サイズ」で、現在主流となっている端末のサイズ10.1~11.6インチが入ります。
保護ケースは含まれていないので、端末を持ち帰る場合には別でタブレットケースを購入するか、オプションで本体に取り付けてある両面テープを使用してランドセル底面に貼り付けるだけの「PC・タブレット用衝撃緩和シート」があります。
ベルバイオスムース カラーステッチ
◆販売価格:63,000円(税込)
◆カラー:全12色
◆サイズ:A4フラットファイル収納サイズ
横幅 23.3cm×高さ 31.2cm×マチ幅 12.2cm
◆主素材:特注ベルバイオ
◆重量:約1,100g

このモデル限定で開発された特注素材のベルバイオが使用されています。最高級イタリア製の牛革のような高級がある風合いやツヤ感が表現されており、人工皮革だからこその軽さもあり、防水力が高く高性能なランドセルです。カラーステッチがポイントになっている人気のランドセルです。
 セイバン 天使のはね
セイバン 天使のはね
教科書やノートなどの教材を入れるメインスペースの大マチは、A4フラットファイルがすっぽりと入ります。高学年になると副教材などさらに教材が増えても安心の収納力です。教材が少ないときには、余った隙間に上靴や給食エプロンなども入れることができるので、手で荷物を持つことがなく両手があきます。
収納可能なタブレットのサイズは約31.0cm×幅約23.5cm以内のものが入ります。
モデルロイヤル クリスタル
◆販売価格:69,300円(税込)
◆カラー:全6色
◆サイズ:A4フラットファイル収納サイズ
横幅 23.5cm×高さ 31cm×マチ幅 12cm
◆主素材:アンジュエールグロス
◆重量:約1,290g

雪の結晶やガラスの靴などの美しいモチーフ、カブセにはスワロフスキー・クリスタルが使用されており、サイドにはティアラをデザインした立体的な刺しゅうがされた、シンデレラのような世界が表現された上品で華やかなランドセルです。
マチ幅が約12cmでたっぷり収納ができ、子ども想いの機能性も高く、お子さんの体に負担のかかりにくい背負いやすいランドセルです。
モデルロイヤル ベーシック
◆販売価格:63,800円(税込)
◆カラー:全4色
◆サイズ:A4フラットファイル収納サイズ
横幅 23.5cm×高さ 31cm×マチ幅 12cm
◆主素材:アンジュエール グロス
◆重量:約1,270g

フォーマルなデザインにアクセントカラーのスマートなシルエットに差し色が大人びたイメージを表現されており、カブセと前ポケット上部には、上品なイメージが漂うレオンの飾り鋲、サイドに入ったトリコロールの王冠刺しゅうがワンポイントになっています。まっすぐ背負えて背負いごこちが快適になる、セイバンならではの工夫がされているので、お子さんの体への負担が軽減されます。
 萬勇鞄
萬勇鞄

大マチが12cmから12.5cmになり、A4フラットファイルはもちろん、たくさんの用具を入れても丈夫な安心の収納力です。
中マチが収縮可能なアコーディオン式で広くなり、収納する物によって柔軟に収納量を変えられるので、10インチ前後のタブレットも問題なく収納できます。また、サイドポケットにはリコーダーや折りたたみ傘など、長い物を収納できます。

ファラーシャ パール系人工皮革

◆販売価格:67,100円(税込)
◆カラー:全4色
◆サイズ:A4フラットファイル収納サイズ
横幅 24cm×高さ 31.5cm×マチ幅 12.5cm
◆主素材:パール系人工皮革
◆重量:約1,250g

素材には光沢のあるパール加工を施した人工皮革が使用されており、背あてのクッションに舞うちょうちょのデザイン(型押し加工)、キラキラした宝石のような華やかなチャーム、大マチに金色の糸とラインストーンで彩られた華やかなちょうちょの刺繍など、ちょうちょがモチーフとなった可憐で華やかなランドセルです。
お子さんが使いやすく安全面なども工夫されているので6年間安心して使用することができます。
ノブレス 牛革

◆販売価格:71,500円(税込)
◆カラー:全4色
◆サイズ:A4フラットファイル収納サイズ
横幅 23.5cm×高さ 32cm×マチ幅 12.5cm
◆主素材:牛革
◆重量:約1,400g

大人でも使いたくなる革製品のカラーを原点にした人気シリーズのノブレスは、落ち着いたカラーのデザインです。
前段ポケットチャームなどの金具はかっこいいブロンズ調に統一されており、内装のチェック柄とブラウン&ブロンズのアクセントが印象的でアンティークな雰囲気のスマートでシンプルなランドセルです。
 ふわりぃ
ふわりぃ
ランドセルの中に荷物が入りきらないときのために、従来のマチ幅11cmから最大13.5cmに容量がアップしました。A4クリアファイルより大きなA4フラットファイル(幅23cm)やタブレットPC(最大幅23×高30cm)が収納できます。
真ん中のポケットは荷物が多いときに全部広げれば最大約5cm広がる「のび~るポケット」が搭載されており、使わないときにはぺったんこにすることができます。
プラチナセレクト
◆WEB販売価格:66,000円(税込)
◆カラー:全10色
◆サイズ:A4フラットファイル収納サイズ
横幅 23.5cm×高さ 30.5cm×マチ幅 13.5cm
◆主素材:クラリーノ レミニカ
◆重量:約1,230g

シンプルでオーソドックスなデザインになっており、マチにハートとリボンをモチーフにした気品を感じさせるシンプルなティアラの刺しゅうが入っているなど、大人っぽいランドセルがいい女の子におすすめです。
軽さ、丈夫さなどの機能性もよく、タブレットも収納することができます。
スーパーフラッシュ
◆WEB販売価格:57,420円(税込)
◆カラー:全15色
◆サイズ:A4フラットファイル収納サイズ
横幅 23.5cm×高さ 30.5cm×マチ幅 13.5cm
◆主素材:クラリーノ タフロック NEO
◆重量:約1,180g

ランドセルの360°全方向から反射するように、さまざまなところに反射材が使用されているので、暗い夜道などでも車のライトがあたると、お子さんの存在がわかる安心・安全なランドセルです。
のび~るポケットが搭載されているので、荷物の多い日にもたくさん入るので両手がふさがらないので安心です。
タブレット収納付きのランドセルは本当に必要?
政府が目標としている、2025年までに完全デジタル教科書化に向けて、多くの学校でパソコンやタブレット端末が取り入れられています。
現在、タブレット収納対応ではないランドセルを使用しているお子さんの場合、すでにタブレットケースに端末を収納してランドセルに入れて持ち運びをしているお子さんもいるので、近年主流となっているA4フラットファイルサイズ対応の大容量ランドセルであれば困ることはありません。
タブレット収納タイプを販売しているメーカーでは、もともとある機能性や品質がいいモデルにタブレット収納の機能をプラスしているものが多いので、これからランドセル購入を考えている方の場合、お子さんがランドセルの中身を整理しやすく「あったら便利」と言った感じです。
また、タブレット端末の中では標準的といわれるサイズは9~10インチですが、学校によって使用する端末が違うので、ランドセルに収納できないサイズの場合があります。ランドセルを購入する前に学校へ確認することをおすすめします。
A4フラットファイルサイズ対応の大容量ランドセルについての詳細は「人気の大容量ランドセルはどこのメーカーがいい?」を参考にしてみてください。
大容量ランドセル+タブレットケースを別で購入もあり!
近年のランドセルはほとんどがA4フラットファイルサイズ対応の大容量サイズになっているので、「大容量ランドセル+タブレットケースを購入」ということも可能なので、それほどタブレット端末収納タイプのモデルにこだわる必要はありません。
大容量ランドセルであれば大マチにケースを収納することができるので、タブレット端末が傷ついたり、落下時の衝撃を和らげたりすることができます。
また、タブレットを収納するケースに、充電ケーブル、タッチペン、イヤホンなどが一緒に入るものを選ぶ方が、忘れ物や紛失を防ぐことができるので安心です。また、ケースに持ち手がついているとランドセルからの出し入れや持ち運びも便利です。

(※セイバン 公式サイトより「タブラスクール 幅広」)
タブレット端末が故障してしまったら修理代は誰がはらうの?

入学する小学校によって違いはありますが、タブレット端末を持ち帰る学校では、基本的にタブレット端末の故障や破損がないように、ランドセルに入れて持ち帰るように言われているところが多いようです。
しかし、タブレット端末をお子さんが日常的に取り扱うということは、大人よりも故障や破損してしまうリスクは高くなりやすく、状況にもよりますが故障や破損した場合、保護者が費用を負担することになり、充電ケーブルやアダプタを破損紛失した場合は各自で準備すると言われると色々と不安になってきますよね。
地域によって補償範囲も違っており、小さなお子さんがタブレット端末を大事に扱わなきゃと思ってはいても、うっかり落としてしまったり、画面が割れてしまうことは起こる可能性が高く、そんなときの補償があるのかどうかはとても気になるところです。
自治体によっては、補償範囲を校内限定での破損は格安の保険でカバー(敷地外は保険加入も含めて保護者負担)というところや、学校敷地外でも修理費用を負担する自治体もあります。
なかには、きちんとした補償がないのならば使わせたくないと思う保護者の方もいるため、気になる方は故障や破損の際の保険などに加入している自治体かどうかの確認をしておくと安心です。
手提げカバンで手がふさがると危険!?
入学する小学校によって違いはありますが、タブレットを持ち帰る学校では、基本的にタブレット端末をランドセルに入れて、その他の入らない教科書や荷物は手提げカバンに入れるように言われているようです。
しかし、荷物の量はその日の授業や学年によって体操服、鍵盤ハーモニカやリコーダー、絵具、習字道具、水泳の用意など、日によって量が変わり、手提げカバンやその他の荷物を持つことで両手がふさがってしまうことがあります。
荷物の重さでバランスが取れずに転んだり、手提げカバンやその他の荷物を持つことで両手がふさがってしまい、転んだときに手をつけずに顔や頭にケガをしてしまったりする可能性があります。
そのため、ランドセルをこれから選ぶ方は、タブレット端末も入れることができ、収納力がある大容量ランドセルを選ぶことで、安全面でのリスクを減らすことができます。
タブレット端末の持ち帰りでトラブル・困ったことはある?
GIGAスクール構想がスタートしたことで、全国の多くの小学校では1人1台のタブレット端末が貸与されて学習で活用されるようになってきました。学校の授業で活用されるだけではなく、家庭での活用も進んでおり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響でオンライン授業になったときも、タブレット端末が活用された小学校もあるようです。
しかし、タブレット端末が活用されたICT教育が進む一方で、子どもが自分で学習以外での端末を利用することによってさまざまなトラブルも多発しています。
・コミュニケーショントラブル
匿名で悪口を書いたり、ネットでの子ども同士のやりとりのなかで子ども自身が傷ついたり、友達を傷つけてしまうことがある
・長時間の利用による健康上の問題
学校のタブレットに制限がかかっていないため、子どもがネットやゲームなどで長時間利用することで依存してしまい、学業や健康への悪影響がある
・不適切サイト(有害情報)の閲覧
子どもが勝手に設定変更や制限解除をして、成人向けや暴力、違法行為など不適切なサイトの閲覧や動画の視聴をしてしまう
・個人情報、プライバシー
子ども自身や友達の写真・動画・住所などの個人情報を公開してしまったり、知らない人に送付してしまうと、アカウント情報を盗まれたり、悪用されることがある
子どもだけではなく、大人でもネットを利用することによってさまざまなトラブルがあります。
お子さんが安全・安心に端末を利用することができるように、大人がきちんとネット利用のためのルールを確認して理解することで、トラブルを避けることができます。
もしも、お子さんがネットを利用していてトラブルが起きてしまったときには、大人に頼るようすることを伝えておきましょう。
【2024年度】おすすめのランドセルメーカーランキング&口コミ
現在、すでにタブレット端末の導入をしていたり、これから導入されることが決まっている小学校へ入学するという方に、おすすめのメーカーや工房系を紹介します。
タブレット端末を収納できるモデルだけではなく、大容量のA4フラットファイル対応サイズであれば、基本的にタブレット端末を収納することは可能なので、ぜひ参考にしてみてください。

フィットちゃんランドセルはセイバンの天使のはねと同じように人気があり、評価が高いランドセルメーカーです。
大手ランドセルメーカーならではの機能性と、色やデザインが豊富なので、「かわいい」「かっこいい」ランドセルがたくさんラインナップされています。
また、数は限られていますがオーダーメイド対応で品質がいいもので低価格なモデルを出しています。
フィットちゃんの口コミ

長女のときにもフィットちゃんでしたが、次女もフィットちゃんに決めました。ラン活の間に他のメーカーのランドセルも色やデザインがどれがいか何度も見に行ったりしていたのですが、フィットちゃんの最新モデルの新色を一目見て娘が気に入ったようでフィットちゃんに決めました。

大容量なので教科書や他の荷物も中に入れることができるので、片道20分の通学路も両手の自由がきくので転んだときも手をつくことができるので安心です。また、背負いやすくする工夫がしてあるので背中のフィット感もよく、少し距離がある通学も体への負担はあまり感じていないようです。
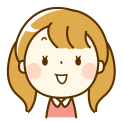
カタログ請求をしてあらかじめ息子とどれがいいか見ていて、デザインやカラーバリエーションが豊富なので迷ってしまいましたが、本体が黒でヘリの部分がマリンブルーの「グッドボーイDX 安ピカッ+楽ッションタイプ」にしました。安全面だけではなく、背負いやすさ、デザインや機能性、価格など総合的にフィットちゃんにしてよかったです。
フィットちゃん おすすめのランドセル
 |
 |
 |
|
期間限定価格 |
期間限定価格 |
期間限定価格 |
 |
 |
 |
|
期間限定価格 |
期間限定価格 |
期間限定価格 |

黒川鞄工房は創業120年の「古き良き伝統ある暖簾(のれん)」と「創業者の理念」が継承された、現在五代目のオーナーである老舗ランドセルメーカーです。
分業化してランドセルを作るのではなく、ランドセルを1人で最初から作り上げられることができる職人さんが、工房で頑丈で美しいランドセルを作っています。
お子さんの健康を考えた「はばたく 肩ベルト」は、肩ベルトを立ち上げることで体感重量が軽くなり姿勢が良くなる効果が期待でき、お子さんの体への負担を軽減することができます。
黒川鞄の口コミ

黒川鞄工房のランドセルはシンプルなデザインで品質が良く、他のランドセルと見比べても高級感があるのでとても満足しています。

品質がいい黒川鞄のランドセルがいいなとは思っていたのですが、体が小さい娘には牛革やコードバンのランドセルは少し重いのでは…と思っていました。でもクラリーノ製の人工皮革のランドセルも販売されていて、黒川鞄の技術はそのままで天然皮革より軽いランドセルを購入できて大満足です。

黒川鞄はカタログ請求や先行予約内覧会などが他のメーカーよりも始まるのが早いので、どこのメーカーのものがいいのか悩んでいる間に、5月頃にはもう完売になっていました。残念です。
黒川鞄 おすすめのランドセル
| シボ牛革 学習院型 軽量仕上 | コードバン 学習院型 軽量仕上 | 軽量クラリーノ F キューブ型 |
|---|---|---|
 |
 |
 |
|
98,000円 |
128,000円 |
68,000円 |
| スムース牛革 学習院型 軽量仕上 | コードバン 学習院型 軽量仕上 | シボ牛革 キューブ型 |
|---|---|---|
 |
 |
 |
|
88,000円 |
128,000円 |
88,000円 |

セイバンのランドセルはテレビのCMでもよく見ることが多く最もシェアが高い、ランドセル業界で最大手のメーカーです。
セイバンのランドセルは機能性が高く、背負うときに子どもに負担をかけないような工夫がされている、総合的にバランスが取れているランドセルメーカーです。
PUMAやコンバースなどのコラボなど豊富なラインナップがあります。
セイバンの口コミ

自宅から小学校までの距離があることもあって、子どもの身体に負担がかからないような機能性のランドセルをさがしていました。3D肩ベルトや左右連動背カンなどの工夫によって、ランドセルの重心が体の中央にくるようにして重さを感じにくくなることもあって、子どもの体に優しいセイバンの「天使のはね」にしました。

元気に走りまわる息子なのでできるだけ丈夫で背負いやすいものをと考えていたのですが、セイバンのランドセルを試しに背負わせてみたところ、背中にぴったりとして背負いやすく、軽く小走りしてもランドセルがバタバタと動くことがありませんでした。デザインもかっこよく息子のお気に入りです。

色や刺繍がかわいいものは他のメーカーでもたくさんありましたが、デザイン、丈夫さ、価格、背中にぴったりと背負いやすいことも含めて総合的にセイバンの天使のはねを選びました。
セイバン おすすめのランドセル
 |
 |
 |
|
期間限定価格 |
期間限定価格 |
期間限定価格 |
 |
 |
 |
|
期間限定価格 |
期間限定価格 |
期間限定価格 |
奈良県橿原市の工房でランドセルを作りつづけて50年を迎える鞄工房山本は、鞄業界では作業の委託・分業が多いなか、一貫製造体制を守り続けており、革の型入れ・裁断から仕上げまですべての工程を、職人さんがこだわりを持って行っています。
21シリーズ全91種類、カラーバリエーションも豊富にそろっており、素材選びから背負いやすさへの工夫、丈夫さ、安全性も高く、6年間飽きのこないランドセルがそろっています。
鞄工房山本の口コミ

シンプルなデザインなのに、金具がハートだったり、カブセの裏地が派手すぎないけど柄が入っていたりなど、いろいろなメーカーのランドセルを見に行きましたが、鞄工房山本のランドセルが一番品質もよくかわいいものが多い印象です。娘は現在5年生ですが今でもお気に入りのランドセルです。

最初は青のランドセルを選ぼうと考えていたのですが、艶消しのマットなブラック生地がとても上品でアンティークブロンズの金具が使用されている「レイブラック」を親子そろって気に入ってしまい、青ではなく黒を選びました。職人さんが手作りしていることもあって、細かいところまでとても丁寧に作られていて、軽くて荷物もたくさん入るなど最高のランドセルに出会うことができて大満足です。

なんとなく落ち着いたデザインやカラーのものが多い印象のランドセルが多いなという印象でしたが、他のメーカーのランドセルも見ていた娘が一番気に入ったのが、「フィオーレコスモス」のハーバーブルーで、色がきれいで本体と違う色の花が目立っててかわいく「絶対これがいい!」と一目惚れでした。
鞄工房山本 おすすめのランドセル
| ラフィーネ | ブロッサム | アンジェール |
|---|---|---|
 |
 |
 |
|
74,900円 |
69,900円 |
74,900円 |
| レイブラック | ブラウニー | オックスフォード |
|---|---|---|
 |
 |
 |
|
69,900円 |
69,900円 |
74,900円 |
千年の伝統を持つ日本一の鞄生産量を誇る鞄の街・豊岡から、高い品質基準を満たした鞄職人の誇りが詰まっている「豊岡鞄」が、2006年に特許庁に認められ地域ブランドになりました。「HAKURA」は、豊岡鞄ブランドと認定された初のランドセルです。
全28色の中から選ぶことができ、天然皮革の滑らかな艶や優しい色合いは、130年の伝統が培った職人技があるからこそです。ランドセルから工業製品の名残である「鋲(びょう)」を無くしシンプルなデザインになっています。お子さんが背負いやすような工夫もされており、高品質で安全性も高いランドセルです。
羽倉(HAKURA)の口コミ

男の子なので黒か紺のシンプルなデザインのものがいいと思って色々とカタログを請求していたのですが、羽倉のランドセルのシンプルなデザインのなかでも他とは少し違う、かぶせ鋲のないシンプルデザインがとても気に入りました。

6年間飽きがこないものを使ってほしいと思っていたので、品質がよくムダな飾りなどがないシンプルなデザインのものを選びました。ただ、少しだけ可愛らしさも欲しいこともあって、ハートのステッチを追加したところ、娘はとても気に入ったようです。

しっかりとした造りで仕上げがとても丁寧というだけではなく、オーダーメイドで娘の好きな色で選ぶことができたのでとても満足しています。また、立ち上がり背カンとS字ベルトのおかげで背負いやすく体に負担がかからないのもうれしいです。
羽倉(HAKURA) おすすめのランドセル
| 羽倉のオーダーランドセル | はねかる | 耐性牛革ウイングチップ |
|---|---|---|
 |
 |
 |
|
64,900円~ |
59,400円 |
67,760円 |
| 耐性牛革スタンダード | はねかる | 羽倉のオーダーランドセル |
|---|---|---|
 |
 |
 |
|
62,700円 |
59,400円 |
64,900円~ |

1950年に創業された池田屋のランドセルは、「厳選したよいものを」「お客様の立場に立ったものづくり」の2つのこだわりを持ってランドセルを作っています。
池田屋のランドセルは、職人さんによる常に背負いやすいランドセルへの工夫や努力がされており、子どもの小さな肩にかかる負担が軽減できるようにすべてのパーツの見直し、形状、素材、動きなどが検証されています。
池田屋の口コミ

荷物で手がふさがらないように大容量で荷物がたくさん入るランドセルがいいと思っていたので、池田屋の水筒なども入ってしまうほどの大きさは安心です。他にはなかなか見ることがない壊れた理由を問わない「6年間無償修理保証」は、ランドセルの品質に自信があるからこそだと思いました。

素材にこだわりがある池田屋さんのランドセルだからこそ、イタリア製の牛革のランドセルの上質さが気に入りました。息子の好きなカラーのステッチを入れたのでシンプルな中にアクセントがあり、また大容量なのでたくさん荷物も入るので安心です。

ラン活で色々なメーカーのランドセルを背負ってきましたが、池田屋のランドセルは背負ったときのベルトの革が柔らかくて、ギボシベルトを採用していて金具が脇腹に当たらないようになっていることもあって「痛くない」というのが息子の感想でした。
池田屋 おすすめのランドセル
 |
 |
 |
|
69,900円 |
75,000円 |
63,000円 |
 |
 |
 |
|
69,900円 |
58,000円 |
63,000円 |
ランドセルを作り始めてから60年になるカバンのフジタのランドセルは、シンプルでカラフルなものが多く、飽きのこない色やデザインだけではなく背あてにも色がついていたりなど、見ているだけでもワクワクする色の組み合せになっています。
アルファベットの「X」のような形状の肩ベルトや背あての部分に背負いやすくする工夫がされていることで、ランドセル本体と背中の隙間がなくなりフィットして体感重量が軽くなっている、お子さま想いのランドセルです。
カバンのフジタの口コミ

体が小さいこともあってできるだけ軽量のものを選んであげたいと思って見つけたフジタのヘリなしのキューブ型ランドセル。本体は黒がいいけど、少し周りとは違うものがいいなと思っていたところ、背あての色がカラフルになっているとてもおしゃれなモデルがあったので購入しました。

毎年、雪がたくさん降る地域なのもあって雪国仕様というフジタのランドセルにしました。牛革のランドセルにしようと思っていたので、雨や雪の日でも水に濡れることを気にしないで使うことができる防水加工は安心です。

シンプルで上品なデザインの牛革のランドセルを私の母と娘が気に入りました。背負いやすさ、耐久性はとても優秀で、現在6年生になりますが型崩れや汚れ、傷なども目立つことはなく使用しています。
カバンのフジタ おすすめのランドセル
| プティハート | ||
|---|---|---|
 |
 |
 |
|
82,500円 |
74,800円 |
82,500円 |
| ブラックキャップス
フラッシュ |
レインボー
フォース |
トラッド
フラッシュ |
|---|---|---|
 |
 |
 |
|
79,800円 |
65,800円 |
83,500円 |
6年間快適に使用できるよう、一番負担がかかりやすい背あてと肩ベルトの部分を頑丈に、職人さんが1つ1つの工程を手縫いで丁寧に仕上げています。牛革やコードバン素材のランドセルにも刺繍等を施すなどデザイン面にもこだわりがあります。
工房系のランドセルはシンプルなものが多いなか、萬勇鞄のランドセルはカラーバリエーションやデザインが豊富にあるので、お子さんの好みに合わせたお気に入りのランドセルを選ぶことができます。
萬勇鞄の口コミ

職人さんの手づくりで仕上げている工房系のランドセルではシンプルなデザインのものが多いのですが、萬勇鞄では刺繍やラインストーンなどの入ったかわいいデザインやカラーが豊富にそろっていたこともあり、牛革で気に入ったモデルのランドセルを購入することができました。重さもそれほど気にならないので、小さい体の娘も負担がかかることなく通学することができています。
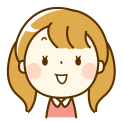
ネットで見ていた色と実際に見た色と違っていたので、やはり質感や背負いやすさなども含めて展示会などで実物を見た方がいいです。実際に見にいったところ、色やデザイン、背負いやすさなど納得のいくものを選ぶことができました。

職人さんの手づくりで品質がよく、デザインやカラーが豊富、安全性などもきちんと考えられていて、他の工房系のランドセルよりも価格が抑えられているという点で比較して萬勇鞄のランドセルにしました。とても満足です。
萬勇鞄 おすすめのランドセル
 |
 |
 |
|
69,300円 |
69,300円 |
74,800円 |
 |
 |
 |
|
71,500円 |
71,500円 |
68,200円 |

1929年に創業したモギカバンのランドセルは、伝統を重んじながらも、時代や環境の変化に対応した先進性を追求した、シンプルなのに存在感のあるランドセルです。
素材へのこだわり、熟練の職人さんの技術、少しでも重さを軽減するためのウィング背カンや、ランドセルのヘリをなくしたキューブ型など、機能性や安全性など6年間安心して使用することができます。
モギカバンの口コミ

牛革のランドセルを6年間使用しましたが、型崩れはなく、目立った傷もなくキレイに使うことができました。品質がいいのに価格もそれほど高くないので、下の子もモギカバンのランドセルを使用しています。牛革なので上の子にリメイクしたものを渡してあげようと思っています。

かわいいデザインのものがいいけど派手過ぎるのは嫌という娘が、いつくかのメーカーのカタログの中からモギカバンのランドセルで「これがいい!」とお気に入りのモデルを見つけました。人気のあるモデルだったので無事に購入することができて一安心です。気に入ったものを確実に購入するためには、早めにカタログ請求をしておくことがおすすめです。

ラン活で色々なメーカーのランドセルを見ましたが牛革のランドセルにしました。決め手は光沢と深みのある素材感と質感で、内張りにはすべてアメ豚が使用されており、本体とかぶせ部が一枚通しの大判レザー仕立てになっていたりなど、他の工房系にはないこだわりを感じることができました。ただ、本革ということもありそれなりの重さがあるのですが、背カンや肩ベルトの形状など、背負いやすくする工夫がされているのでそれほど問題はないようです。
モギカバン おすすめのランドセル
 |
 |
 |
|
72,000円 |
65,000円 |
63,000円 |
 |
 |
 |
|
69,000円 |
69,000円 |
82,500円 |

老舗のランドセルメーカーである株式会社協和の「ふわりぃ」は、何よりもお子さんを最優先に考えた「子ども第一主義」の背負いやすいランドセルを作っています。
成長とともに変わっていく体型・身長などにも対応できるように作られており、障がい児用のUランドセルも高い評価を得ています。
また、オーダーメイドランドセルは、6年間使えるランドセルが自分の好きなデザインや柄にできるため特に人気が高くなっています。
ふわりぃの口コミ

周りにいる先輩ママに聞いたところ、ふわりぃを使用している方が多かったので、実物を見てみようとお店にいきました。実際に娘に背負わせてみると、作りもしっかりしていて背負い心地もよく、デザインや機能性もいい、さらに価格もお手頃ということもあり決めました。

大手のランドセルメーカーですが、他のメーカーのものよりも価格が安く、シンプルなものからデザインやカラーも豊富なので息子が気に入ったものを選ぶことができました。

たくさんの場所に販売店があって展示会もやっているので、自宅から近いところに実際に足を運んで手に取って背負い心地などを試すことができました。いろいろなメーカーのランドセルを背負ってみましたが、ふわりぃが一番背負い心地がいいとのことだったので購入しました。
ふわりぃ おすすめのランドセル
| スーパーフラッシュ | プラチナセレクト | ロイヤルコレクション |
|---|---|---|
 |
 |
 |
|
WEB価格 |
WEB価格 |
WEB価格 |
| スーパーフラッシュ | プラチナセレクト | スーパーフラッシュ フィーバー |
|---|---|---|
 |
 |
 |
|
WEB価格 |
WEB価格 |
WEB価格 |